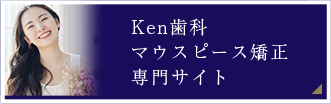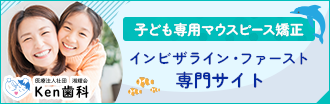みなさんこんにちは。
藤沢市の歯医者【Ken歯科】です。
「子どもの歯並びが気になる……。」
「歯並びを整えるために、できることをしてあげたい。」
と考える保護者の方も多いのではないでしょうか。
歯並びに関しては骨格による遺伝的な要素も多少ありますが、実は毎日の「食べ方」や「噛み方」などの生活習慣も大きく関係しています。
そこで今回は、「子どもの食べ方は歯並びにどう影響するのか」「なぜ食育が大切なのか」について、お話させていだきます。
目次
■毎日の食べ方が歯並びに与える影響とは
歯並びのバランスは、「顎の発達」と密接に関係しています。
そしてこの顎の発達に影響するのが、お子様の食べ方です。
具体的には、以下のような要因が歯並びの乱れを引き起こすことがあります。
◎やわらかい物ばかりを食べる
しっかり噛むことで顎の発達が促されますが、やわらかい物ばかり食べると、噛む回数が少なくなり、顎の骨の成長が不十分になる場合があります。
◎口を開けたまま食べる(口呼吸)
食事中に口が開いたままになっていると、口呼吸が習慣化されやすくなります。すると、舌や頬の筋肉のバランスが崩れ、歯に余計な力がかかることで歯が傾く・歯並びが乱れる原因になることがあります。
◎丸のみしてしまう
ほとんど噛まずに食べていると、 噛む力や顎の筋力が育たず、歯列不正につながりやすいです。
また、長期間になると、食べ物が細かくならないまま胃へ送られ、胃腸への負担も考えられます。
◎片側ばかりで噛む
食事をする時は、左右バランス良く噛むことが大切です。
かみ合わせのバランスが崩れ、顔のゆがみや顎関節のトラブルを引き起こすことも考えられます。
このように、毎日の「噛む力」や「咀嚼の習慣」が、将来の歯並びに影響するのです。
■食育の基本と歯並びへの関係
「食育」とは、子どもたちが正しい食の知識と習慣を身につけるための教育のことです。文部科学省などが推進する食育基本法でも、健康な成長や生活習慣病の予防と並んで、歯や口の発達にもつながると言及されています。
歯科の立場から見ると、食育は単に「栄養を考える」だけでなく、「しっかり噛んで食べる力を育てる」ことが重要になります。
特に乳幼児期から小学生までの時期は、顎の骨の成長が活発で、噛む機能を高めるのに適した時期です。
正しい食べ方を習慣づけることが、自然と歯並びの安定につながります。
■毎日の食事で意識したい4つのポイント
①ひとくち30回を目安にしっかり噛む
顎の発達を促し、消化にも良い
②左右両方の歯でバランス良く噛む
かみ合わせのバランスが整いやすい
③背筋を伸ばして正しい姿勢で食べる
-
床に足の裏をがつくように座り背筋を伸ばした姿勢で食べることで、姿勢が安定し、しっかりと噛みやすくなる
-
舌や頬の筋肉もバランスよく使えるようになる
④食事中のテレビ・スマホは控える
よく噛むことに集中できる環境づくりを整える
一見当たり前のようですが、現代の生活スタイルではなかなか意識されにくいポイントでもあります。特に食事中のスマホ使用は姿勢も悪くなりやすいため注意が必要です。
■歯科医院でのアドバイスも活用を
歯並びの心配がある方や、子どもの食べ方が気になる方は、小児歯科や矯正歯科でのチェックもおすすめです。
歯科医院では、単にむし歯予防だけでなく、口腔機能(咀嚼・嚥下・発音など)の育成にも力を入れているところが増えています。
日常の生活習慣や癖が歯並びの不正につながることもあるため、歯並びが悪くなる癖は早期に発見して改善することが望ましいです。
定期的なチェックによって、将来的な矯正の必要性を軽減できる可能性もあります。
■毎日の“噛む力”が歯並びの未来を変える
子どもの食べ方は、見た目の歯並びだけでなく、かみ合わせや顔立ち、全身の健康にも関係する重要な要素です。
食育を通じて、よく噛む習慣を育てることは、将来のむし歯や歯並びのトラブルを防ぐための“先行投資”ともいえるでしょう。
当院では、管理栄養士や歯科衛生士による食事指導も行っておりますので、疑問や気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
お子様の口腔の健康を守るためにも、日々の食事習慣を今一度見直してみましょう。