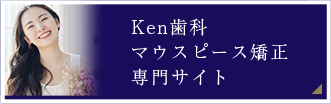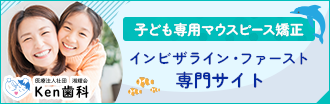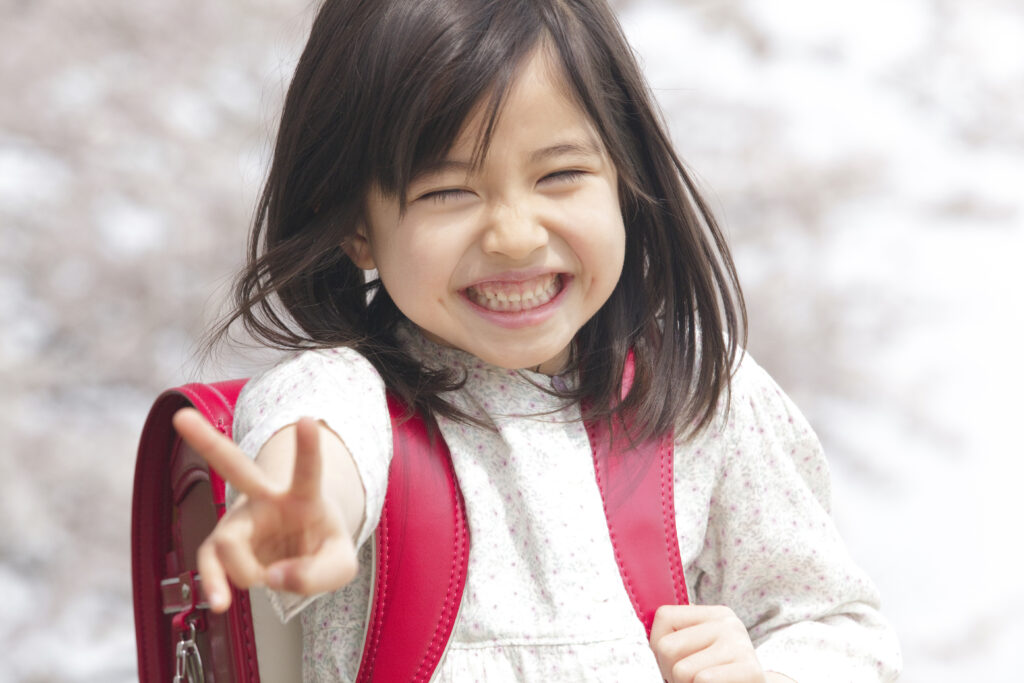
みなさんこんにちは。
藤沢市の歯医者【Ken歯科】です。
お子様の矯正治療で使われる マウスピース型矯正は、目立ちにくく取り外しができるのがメリットです。
しかし、「学校で外したときにマウスピースを失くしてしまう」というトラブルも少なくありません。
そこで今回は、学校生活の中でスムーズに矯正を続けられるように、マウスピースを正しく管理する工夫や注意点をご紹介します。
目次
■お子様の学校生活とマウスピースの付き合い方
マウスピース矯正は、1日20~22時間以上の装着が推奨されます。
そのため、食事や歯みがきの時間を除いた日中の学校生活でも装着を続ける必要があります。
しかし、学校生活でも食事の際にマウスピースを外すタイミングがあります。
特に小中学生で多いのは、うっかり机の上やポケットに置いたまま紛失してしまうケースです。
■学校でマウスピースをなくさないためにできる工夫
◎外す時は専用のケースに入れる
学校にいる時だけでなくマウスピースを外した時は、必ずケースに入れる習慣をつけましょう。
これは、家にいる時も同様で、ティッシュにくるんでおいておくと、誤って捨ててしまう可能性があります。
また、落とした時にもわかるように、ケースに名前も記載しておくと安心です。
◎小さなポーチにまとめて管理する
歯みがきセットとマウスピースケースを一緒に入れて小さなポーチに入れておくのも紛失を防止するひとつの方法です。
歯みがきの時にマウスピースもスムーズにケースに入れることができ、食事をした後にまとめて持ち運べるため、紛失防止につながります。
■お子様が意識できるようになる工夫
お子様の矯正を成功させるためには、保護者の方のサポートだけでなく、お子様自身が意識を持って取り組むことが大切です。
◎ご家庭でシミュレーションする
給食の時間を想定して「外す→ケースに入れる→歯みがき→装着」という流れを練習しておくと、学校でも自然に行動しやすくなります。
◎慣れるまで毎日の声かけ習慣
「学校で外したらケースに入れた?」と帰宅後に確認してあげることで習慣化が進みやすくなります。
◎付箋を活用する
ランドセルやかばん、筆箱などよく目にするところなどに「マウスピースケース」と付箋をつけておくと、忘れにくくなります。
■年代別の環境に合わせた対応
◎小学校1~3年生頃
保護者の方のサポートが特に重要な時期です。
マウスピースケースやポーチの管理を徹底するようにしましょう。
◎小学校4年生頃~
自分で管理する意識を持てるよう、紛失や破損の責任を理解できるように説明しましょう。
歯並びが良くなるとメリットが多いことや、きちんとマウスピースをつけないと治療計画通りに歯が動かず、治療期間が延びてしまうことなどを理解してもらうことで、紛失防止にも役立ちます。
■マウスピースを失くしてしまったときの対応
注意して管理していても、マウスピースを紛失してしまう場合もあると思います。
その場合の対応についてご紹介します。
◎歯科医院に連絡する
装着時間・装着日数などによってどのような対応になるか異なります。
紛失してしまった場合には、歯科医院に連絡して対処法を確認しましょう。
◎教室、給食の場所、歯みがきをした場所を探す
マウスピースを外した可能性のある場所を探しましょう。もし誰かに踏まれてしまって形が変形・割れている場合は、無理に装着せず、歯科医院に連絡して適切な対処を仰ぎます。
インビザラインの場合、治療計画に応じて「次のステップのマウスピースに進めるか」「新たに再作製が必要か」を歯科医師が判断します。
もし、紛失した時の流れを知っておくと、スムーズに対応しやすくなります。
■安心して子どもの矯正治療を進めるために
お子様の矯正でマウスピースを使用する際、学校生活の中で「マウスピースを外す」場面があります。
「マウスピースケースに入れる」「マウスピースケースと歯みがきセットをポーチに入れる」「お子様に習慣化してもらう」といった工夫で紛失や破損のリスクを軽減できます。
保護者の方が協力し、子供自身も管理できるようになることで、治療がスムーズに進み、理想的な歯並びへと近づけます。お子様の歯並びや矯正のことでお悩みがある方はお気軽にご相談ください。